テディ・ベア大英博物館おへんろ グレイソン・ペリー
すりきれた50歳のテディ・ベアとアーティストのバイク巡礼、この展覧会はそこから始まります。
おとぎの国の乗り物のような改造バイクの背には小さな祭殿が備えられ、
なかにテディ・ベアがローマ皇帝のように腰掛けています。
運転するのは、ライラック色のキュートなコスチュームに身を包むアーティスト。

2003年、陶芸作品でターナー賞を受賞したGreyson Perry (グレイソン・ペリー)は、
少年時代からクロス・ドレッサー(異性装)でした。
テディ・ベアは半生をともにした彼のヒーロー。
小さなぬいぐるみはペリーの「男性性」の体現であり、
女装するペリーはもうひとつの彼のアイデンティティなのです。
子供の頃から社会に映し出された自分と自分の内面との対話を繰り返してきたペリーは、
アンビバレントな自己を通して見える世界観を、陶芸作品のになかに表現してきました。
今回の展覧会は、グレイソン・ペリーと大英博物館コレクションの名もなき職人たちとのコラボレーションです。
全世界のあらゆる時代からこの博物館に運び込まれ、倉庫に眠っている作品を、
彼は、手にとり、インスパイアされ、作品をつくり、
そして、それらのコレクションといっしょに自身の作品(新旧含め)を展示しました。
たとえば、「Shrine」のコーナーでは、
古代エジプトの「ソウル・ハウス」に、チベットのストゥーパ、
日本の路地にある小さな神社に発想を得たペリー自身の作品、といった具合。
彼は、文化の「Give and Take」に焦点をあてます。
いつの時代も文化は境界を越えて交流し、他者の影響を受け、また、与えてきたのだと。
その意味で、日本は他文化を吸収し、新旧を融合させる名手だと賞賛します。
彼が創った小さな神社には、屋根からダイアナ姫の肖像とNYの世界貿易ビルの絵が絵馬のようにぶらさがり、内陣の額絵にドイツの冬の風景を髣髴とさせる(キーファーの絵のような)ミニチュア画、
さらにその奥にテディ・ベアが鎮座しています。
「展覧会のテーマをもっともよく表している一点」と彼がコメントするのは、
お遍路の格好をしたハロー・キティのタオル(大英博のコレクション!)。
何百年も続く伝統が現在のアニメと融合することに、文化の有機性や継続性をみるのです。
ペリーはまた、展覧会のもうひとつの主役は、鑑賞者のイマジネーションだと主張します。
展示のラベルには、学芸員や専門家たちの解説はいっさいありません。
代わりに、作品に対するペリー自身の見方やそこから繰り広げられる独自の世界が、
彼自身の言葉で添えられています。
それも全部ではない。収集地や制作年代という基本情報のわきにある空白の部分は、
鑑賞者ひとりひとりが、心の中で、
「あながた観ているものに対するコメントを書いて・描いてください」と促しているかのようです。
ペリーのコメントに刺激されて、わたしの心もかきたてられました。
なんだか懐かしい気持ちです。
字も満足に読めない子供の頃に、父に連れられて行ったミュージアムで、
いろいろなものを見て、想像を膨らませたあの感覚を、すこしばかり取り戻したかのような、、、。
もちろん、学術的で歴史的背景の手がかりがあるほうが
、展示されたものを深く、しかも、正確に知ることができるというのも、事実です。
でも、この展示は、わたしたち個人の理解というものは、
もっと直感的で、脈略もないほど多様で、自由であってよいということを思い出させてくれる。
逆に、ミュージアムの機能というものを、違う角度から見直すきっかけをつくったのかもしれません。
大英博物館のプラス面とマイナス面を示唆するようなペリーの作品も展示されています。
その名も、「ロゼッタの壷」ーもちろんおわかりですね。
大英博の大目玉「ロゼッタ・ストーン」をパロッてること。
「ナイスなお出かけ/ 植民地主義 / アイコニック・ブランド / 学校見学 / サッチャーズ・チルドレン / 寺院としてのミュージアム、、、」
丁寧につくられた、黄色の美しい壷のなかに、そんな言葉が埋め込まれています。
プライベートな巡礼ではじまった展覧会はユニークな旅をたどり、
最後のコーナーは、アーティストがこの企画に寄せて新たに創った「名もないクラフト・マン(名工)たちの墓」という、展覧会と同名の作品で終わります。
船形の墓には、エジプトの棺や中国の彫刻、サクソンの武具、アフリカの頭部像など、
大英博のコレクションのコピーで埋められ、
上部には、作り手の血と汗と涙を表すボトルがたくさんぶらさがっています。
「これは世紀を越えて、世界が驚嘆するようなものをこしらえてきた名もなき名工たちの記念碑です」
と、書き添えられています。
ここには、アイデンティティのもうひとつの両義性があるのではないでしょうか。
つまり、陶芸作品を通して現代美術のスターダム入りした彼自身の立ち位置です。
西洋美術史において、クラフト(工芸)とアート(美術)のあいだには深淵な境界がありました。
伝統的に、アートのためのアートは作り手の名前が歴史に残り、
クラフトのほうはほとんどの場合残りませんでした。
TATE美術館が主催する現代美術のターナー賞において、
陶芸ジャンルの作家が入賞すること事体も、初めてのできごとだったのです。
かたや、大英博物館には、作り手の名前などさほど重要視されないアーティファクト(工芸品)が、集められてきました。
このことは、博物館と美術館の境界についての議論ともつながっています。
グレイソン・ペリーは、そのことを踏まえて、
いまやセレブなアーティストとなった自分自身が、
世界のクラフト・マンたち、彼にインスパイアを与えてきた名もなき作り手たちに、
敬意を込めてこの作品を創ったのではないでしょうか。
博物館に展示されたものは、創りあげられた結果としての「もの」でしかないと、
わたしたちは見てしまいがちですが、この展示はそれを創った人々に光を当てようとしたのです。
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、現地ロンドンにて、個人旅行の企画・ガイドや
日本/英国のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。





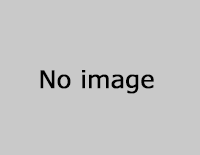






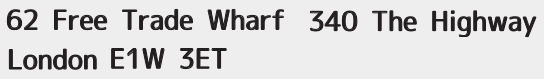

コメントを残す