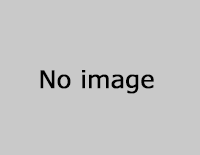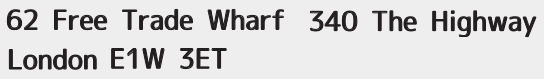私たちが生きる時代を撮る、ヴォルフガング=ティルマンス
時を忘れた。思いもよらず見入ってしまった。
写真の展示でそんな経験をしたのは、何年ぶりだろう。
何に魅了されたのか−すぐに答えがみつからなかった。
でも、そうやって美術館を出た後々まで、
「なんでわたしは魅せられたわけ?」と、答えを探さないではいられない展覧会が好きだ。
だから、こうやって拙い言葉でつなげとめようとしている。
テート・モダンでの「ヴォルフガング=ティルマンス(Wolfgang Tillmans)2017」展。
よい展覧会はいつも最初の部屋から惹かれてしまう。今回もそうだった。
ひとつひとつの作品は、
何気ないホテルの一室・島が浮かぶ星空・赤い車のヘッドライト・アラブの街のマーケットの様子・カニとハエのクローズアップ。。。
なんの変哲も、なんの主張もない写真にみえる。
そんな日常的なものがショッキングに新鮮なのは、
まるで宇宙人がみるように捉えているからだ。
宇宙人がはじめて地球に降りて、今までみたこともない世界を留めておきたいと思ったら、
こうなるんじゃないかという写真なのだ。
わたしたちは、レンズを構える前に、すでに「車」というものを知っている。「カニ」という存在も知っている。
当たり前すぎて気が付かないのだけど、
そういう知識が先にあって、その「知識のフレーム」の中で写真を撮る。
車なら車のように、カニならカニのように。
でも、ティルマンスは違う。その「アングル」も「切り取り方」も、何が彼の視覚レンズに映るかも。
もちろん、彼は宇宙人ではない。
逆にいうと、そのような知識のフレームを取っ払うのは並大抵の事じゃないだろう
−そこに彼が単なるカメラマンではなく、アーティストである所以がある。
そうやって撮った写真作品は、
マクロで同時にミクロ、知的でかつ感覚的、アブストラクトで写実的。
そして部屋にあるすべての作品が、
被写体も手法も大きさもバラバラなのに不思議に響き合っている。
写真一点一点で完結するのではなく、
部屋全体がひとつのインスタレーションとして作られ、
そこに詩がある。
思うに、ひとつだけ、彼が宇宙人から人間に戻るジャンルがあった。
それは被写体が人間の時だ。
彼の恋人を撮る時、パーティーのグループを撮る時、街の民衆を撮る時。
彼は宇宙人から人間に戻って、人の存在の愛おしさやはかなさや強さを表現しようとする。
でも、その人を被写体にしたものが、アブストラクトな写真や、植物、海面、建築物などと、同じ部屋で結ばれた時は
また、あの彼独特の詩の世界のひとつとなる。
ヴォルフガング=ティルマンスは1968年生まれのドイツ人、イギリスの美大をでて、2000年にターナー賞を受賞した。
現在もロンドンとベルリンを拠点にするアーティストだ。
日本でも何度か個展が行われたらしい。
もうひとつ、わたしが魅了された理由は、
彼の表現に、わたしたちが生きている「現在」に対しての、アーティスティックな問いかけが込められている事だ。
イラク戦争−その大義となった「殺戮兵器の存在」をめぐる、「真偽」というそのもの、
日本海の領海水域問題の緊張をめぐって、その根本にある「領域」という考え方そのもの、
ゲイの差別や解放運動をめぐっての「ジェンダー」とは何か、
トランプ政権の誕生−ポピュリズムをめぐっての社会の危うさ。
アートに政治を持ち込むなんて、とお思いだろうか?
でも、アートは歴史を通して常に政治的でその時の社会を反映していた。
ダ・ヴィンチもカラバッチオもレンブラントもゴヤもマネもゴッホもピカソも。。。
彼らは時代や社会から目をそむけはしなかった。
政治的な主張をしたのではなく、
他のメディアとは違う視点から、彼らが生きた「時代/世界」をみせつつ、
人々にしっかりと自分で考えるよう、誘ってくれた。
ヴォルフガング=ティルマンスもまた、
今回の展覧会を通して、
今わたしたちが生きている社会を、一歩ひいた位置から違う「アングル」「切り取り方」「レンズ」で問い直してくれる。
Wolfgang Tillmans 2017
Tate Modern
Unitil 11/06/2017