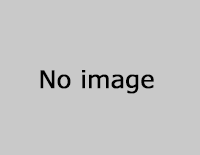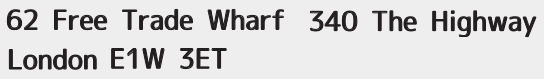母のいる空間:ジャコメッティー展
部屋の真ん中に、老いた母がこちらを向いて座っている。
母の身体を描く線が自由に伸び、その周囲に広がり、
椅子やカーペットや柱時計や部屋のすみずみまでつくったかと思えば、
今度は、その線が母に戻ってきて、また彼女の身体やまなざしの周りで渦巻く。
母を中心に部屋の宇宙ができていて、もはや母がこの家だ。
いや、彼女が部屋になったのかもしれない。
確かなことは、この空間に一人の老いた女がいるということ。
今わたしがみているのは、ジャコメッティが描いた彼の母の肖像画である。
ロンドンの肖像画美術館、特別展示の一室でのこと。
そこには、彼の描いた肖像画と一緒に、あの特有の細長い人体の彫刻が並んでいた。
平面の肖像画も立体の彫刻も一体になって響きあっている。
母と母がいる部屋を描く神経質な線からは、粘土をつけたり、削ったりするアーティストの手の動きがみえる。
平面だろうが立体だろうが、彼にとって追求するものはきっと同じなのだ。
ジャコメッティがモデルにするのは、母のほかに妻アネッティや弟のディエゴといったごく身近な人々。
個人としてのモデルが、彼の手にかかると普遍的な人間像に生まれ変わる。
アーティスト自身もこう残している。
「ずっと一緒に仕事をしてきた弟を何度も何度も描いているうちに、目の前の人が弟であるという意識が消えてしまうのだ」と。
ジャコメッティーといえば、有名なのは巨大でやせ細った「歩く人」や「立つ人」だろう。
そのブロンズの人体像は、ありえないようなデフォルメで細長く表現されたいるのだけれど、
なぜか、まさに「人がそこにいる」と思わせる不思議なリアリティーがある。
残念ながらこの展覧会ではそのような巨大な全身像はなかったけれど、
これだけの数の肖像画と小ぶりの人体彫刻をまとめてみることで、
そのリアリティーがどこからきたのか、少しわかったような気がした。
若い頃から彼は同じモデルを使って、何体も何枚も肖像をつくった。
あらんかぎりの集中力で観察し、作り上げていくのに、
目の前の表情は雲を掴むように消えてしまい、また新しい表情が現れる。
だから、その人の印象を自分の作品に仕上げることが出来なかった、と彼は言う。
シュールリアリズムに向かったこともあったけれど、そこには自分の求める答えはなかった。
そして、再びリアリズムに戻った。なんども作っては壊し、壊しては作った。
ある時、自分の恋人を窓の外、遠目に見かけた。
パリの道端で、彼女はとある空間のなかに立っていた。
その時の印象をそくざに小さな彫刻にこめた。
それをマッチ箱の中にいれ、戦争で故国スイスに逃れた時ももっていった。
そのマッチ箱の小さな像を眺めながら、恋人の記憶をたどりながら、
女性の人体像をつくってみたが、それは彼がパリでみた彼女ではない。
何度も何度も作り直していく上で、気がついたら巨大な像になっていった。
そして不思議なことに、巨大な像になってはじめて、かつての恋人のリアリティーを感じたのだという。
彼と同時代に生きたサルトルは、戦後はじめてのジャコメッティの展覧会のカタログに序文を寄せている。
そのなかで哲学者は、ジャコメッティの巨大な細長い像にこそ戦争を体験した人間の実存をみるとかいた。
そうなのかもしれない。
戦争はそれを生きたすべてのアーティストにとって避けてはとおれない人間の真実だ。
でも、今回の展覧会をみて、わたしは、
ジャコメッティーが、そんな大きな哲学をもって作品づくりにとりくんだというよりは、
モデルを執拗に観察し、その周囲の空間を捉え、「その人がそこにいる」という彼がみた印象を作品に表そうとした。
ただただ、それを追求しただけなのではないかという気がした。
できあがったものが、結果的に、サルトルや現代人にとって普遍的な人間像に映ったのだろう。
アーティストのなかには、その時どきの芸術の奔流には流されずに、
自分自身の目や考えだけを信じて、自分の表現をつきつめていく孤高の人がいる。
ジャコメッティーは間違いなくその一人だと思う。
ロンドン 国立肖像画美術館
2016年1月16日まで
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や
日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
ご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。