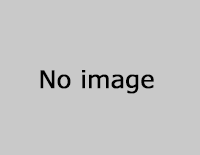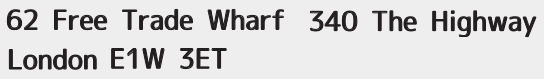フェイス・オブ・ブリテン-英国の顔
「イギリス人であるとはどういうこと?」
「肖像画って何?」
肖像画美術館で開催中の特別展、『FACE of BRITAIN』は、そんな疑問をまっすぐに問いかけてくる。
-副題には、『肖像画を通してみるNation (国民国家)』とある。
イギリスは言うに及ばず、どの西洋諸国も今や多民族が共存する国家だ。
片や待ったなしの移民問題やイスラムとの軋轢で、
「ある国の国民である」とはどういうことなのか-そんな根本的な問いにわたしたちは揺さぶりがかけられている。
だからこそ、欧米のミュージアムでは、アイデンティティー問題を問う展覧会がますます増えてきたのだろう。
翻って、この問題は私自身にも身のつまされる問いでもある。
日本で生まれ育ち、40代になってからの留学がきっかけでイギリスに渡り、この国に家族をもち、生活をし、おそらく骨を埋めるだろう、
では、わたしは日本人なのかイギリス人なのか?
どこまでいっても根無し草のよそ者でしかないのではないか?・・・
片や、アイデンティティーを巡るミュージアムの問題は、実はわたしの研究テーマでもある。
そんなわけで、これまでたくさんの展覧会をその観点から観てきたわけだけれど、
アイデンティティーという難問を、ミュージアムの展示のなかでいかに公平公正に物語るのか-失敗するケースも少なくない。
そんな中、この『FACE of BRITAIN』は、内容、解釈、構成、すべてにおいて優れた展覧会だったと思う。
展覧会は、5つのテーマで構成されていた。
「Power」を表す肖像画 ・ 「Love」を謳う肖像画 ・ 「Fame-誉れ」を促す肖像画 ・ 普通の「People」を捉える肖像画 そして 画家自身の「Self」を見つめる肖像画。
どれもが内容の濃い展示だったけれど、このブログでは、特に興味深い作品や新しい解釈があった「Love」「Self」「People」の展示室について触れたい。
例えば、「Love」
- 愛する者をモデルに、画家に絵を依頼する事は、よく知られた肖像画の役割だろう。
だが、時には、他界した者、二度と出会えぬ者を永遠にそばにおいておきたいという、測りがたい熱情がこめられる事もある。
数時間後には射殺されるジョンがヨーコと抱き合っているシーンを捉えた写真も、
あるいは愛する若妻が亡くなり、彼女の体がまだ温かいうちに画家ヴァン・ダイクを呼び寄せて描かせた絵も、その思いを伝える。
写真が開発されたヴィクトリア時代には、死んだ子供を撮影して家族のアルバムの中に入れる習慣があったのだそうだ。
当時は幼い子供の死亡率が現代人の想像を絶するほど高かった事を思いおこせば、
その家族アルバムの存在自体に心を動かさずにはいられまい。
自分自身をみつめる内省的表現も肖像画の永遠のテーマだ。
「Self」の展示室には、
女性の社会的な地位がまだまだ低かった19世紀の一女性画家の自画像から、
自らの血を使って赤い頭像を作った現代アーティスト、マック・クィーンまで並んでいた。
中でも目をひいたのは、イギリスで生み出された最も初期の自画像だ。
小さな板に描かれた二人の男性像。
パレットをもっているのが画家フリッケ自身。隣で楽器をもっているのは牢獄で一緒だった画家の友人だ。
この絵は、牢獄(ロンドン塔?)に二人が捕らわれの身だった時に描かれたものと、解説される。
どちらかが処刑された後、友を覚えておきたい、自分を忘れないでほしい、という願望がこめられているのだろう。
その願いは、他者の眼を通して永遠に行き続けたいいう、人間の根源的な思いと通じている。
「People」の展示室は、
歴史的、社会的な有名人ではなく、名も無き人々をとらえた肖像に焦点をあてる。
鑑賞者が目にするのは、奴隷として連れてこられ自由市民になったイスラム教徒、ロンドンで差別と闘った黒人と白人のカップル。
極端に背が高い男性など、いわゆる「フリーク」と言われた人々・・・。
興味深かったのは、イギリス特有の作品を生み出したウィリアム=ホガースの描いた肖像画だった。
王侯貴族を描くことが肖像画のそもそもの役割だったが、
18世紀になり演劇が流行ると、有名な俳優もその対象になり始める。
ところが、ウィリアム=ホガースが描いたのは舞台の上のセレブリティーではなく、芝居を観にくる普通の人々の様子だ。
明日には死刑になるという女性を描いた彼の版画も展示されている。
この部屋には、ホガースのほかにも、「人間」の多様性や彼らのバイタリティーに興味をもち、社会全体を見抜こうとするアーティストたちの眼差しがある。
ことほどさように、ひとつのテーマを扱った展示室もおおいに面白かったし、
そこで選ばれた展示品や展示がつくるストーリーからも新しい発見があった。
さらに付け加えなければいけないのは、
この期間限定の特別展示が、別に設えられた企画展示室にまとめられたのではなく、
常設展示室のあちこちに散らばった5つの小部屋が、この期間だけいつもの展示を外して、そこに持って来ている事だ。
そうすることで、来館者の経験がまとまりのない断片的なものになるかもしれない。
だけれど、この意図的な構成によって、常設展示に飾られた他の肖像画作品に対しても、新しい光があたるのではないか。
思えば、「肖像画美術館」そのものが、王侯貴族や政治家、偉人賢人などの肖像を並べることで、
まさに「英国性」というまとまったひとつのアイデンティティーを育てる場として機能してきた。
この「フェイス・オブ・ブリテン」は、
そのようなまとまったアイデンティティーがあるわけではなく、
わたしたちの社会は、歴史上常に、多様で、流動的な人々の像が共存してきたし、
今まさにそのような波の中にあるのではないかと問いかけている。
もし、あえて「英国性」というものを見つけようとするのなら、
「Love」や「Self」といった、いわば肖像画の普遍的なテーマで構成されることで、
そのテーマの下に選ばれたひとつひとつの顔が交錯するなかに、見え隠れするのだろう。
ロンドン肖像画美術館 2016年1月4日まで
http://www.npg.org.uk/whatson/simon-schamas-face-of-britain/exhibition.php
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や
日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
ご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。