「踊り子の画家」へのアングル:ドガとバレエ展
ひとりの画家に焦点を当てた「個人展」が、わたしは好きです。
あるテーマのもと、複数のアーティストを比較したり、芸術や社会を複合的に捉えたりする、
いわゆる「テーマ展示」が盛んになったご時勢ではありますが。
目からウロコがとれる展示といえば、「テーマ展示」に軍配があがるのかもしれません。
それからすると「個人展」はオーソドックスで、だから新鮮味に欠けると思われがち。
それでも、そのストーリー展開に惹かれる理由は、
ある芸術家の作品ひとつひとつをじっくりと鑑賞し、その考え方や技法の変化を知ることができるだけではなく、制作の喜びや苦渋、家族友人との関係、彼・彼女が生きた社会、それが作品にどのような影響を与え、
作品が社会にどういう意味をもたらしたのか、総合的にみることができる
―展覧会を見終わって、充実した時間を過ごせたと感じることが多いからです。
振り返ってみると、こうした個人展はほとんどの場合が、
一芸術家の制作の過程をなぞる‘時間軸’構成でした。
そうでなければ、日本の美術館がよくやるように、「○○と同時代の画家たち」てな感じの、
近い時代に活躍した芸術家たちの作品をいっしょに並べ、互いの影響を明らかにする手合いのもの。
ところが、昨今ヨーロッパでは、
時間軸とは違うアプローチで構成された個人展が開かれるようになりました。
そういう新しいタイプの個人展は、腰の据わった取り組みのなかにも、静かな挑戦がみらるのです。
ロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで開催中の「ドガとバレエ」展がまさにそのような展覧会でした。
「踊り子たちの画家」として知られたドガゆえに、「ドガとバレエ」という主タイトルはすんなり響きます。
かたや、「Picturing Movement(動きを描く)」というサブタイトルは、展示の明確なアングルを示しています。
つまり、彼が動きというものをいかに絵画という静的な表現に落とし込もうとしたかを、
この展示はみようとしているのです。
さらに興味深いことに、ドガが生きた時代に誕生した技術、写真や映画との関連も描いています。
たとえば、「Mobile Viewing」という展示室の中央には、著名な彫刻「14歳の踊り子」が置かれており、
周囲の壁には同じポーズをとった少女を360度違う角度から描いた素描が並べられていました。
どのような視線で14歳の踊り子が捉えられ、彫刻に命を与えられたのかが読み取れます。
その部屋の一角では、周囲に設置された多数のカメラで中心のモデルを捕らえ、
撮影された複数の写真から彫刻をつくるという当時の実験も紹介されていました。
「The Dancer in Movement」では、位置の定まった体に何重にも異なる手足の線を描いた素描や、
ひとりの踊り子の別の瞬間の体の線が同じ画面のなかに展開する油彩画など、
ダンスのムーブメントを平面に表そうとするドガのチャレンジが紹介されています。
また、同じ部屋には、映画の第一人者、ルミエール兄弟の踊り子を映し出した作品が流れています。
別の一室には、踊り子たちを写したドガの写真作品が展示され、
撮影された踊り子と同じポーズを描いた素描や彫刻も並べられています。
展示の解説にあるように、彼は写真や映画という新しいテクノロジーに対して、
一定の距離をおきながらも、自分の芸術制作にその技術や対象の捉え方を取り入れようとしたのです。
このように、あるアングルから芸術家を検証するわけだから、
他の角度からみえるドガ像が薄れてしまうのは当然のことでしょう。
たとえば、ジャポニズムの影響とか、印象派の発展に果たした役割とかについては、光が当たらない。
会場の入り口で展示構成の図をみたとき、
わたしがもっとも危惧したのは、科学的な分析を取り入れることで、
ドガの人間性がみえにくくなり、どこか血の通わない展示になっているのではないか、ということでした。
ところが、展示会場も終わりに近づいたときそんな心配は消えていた。
ドガという芸術家に親しみを抱き、充実した読後感に酔いしれている自分に気づいたのです。
なぜだったのか、日がたって考えてみるのですが、
まず何よりもドガの視線に近づけたことでしょう。
ひとりのモデルを描いただけの小さな素描をこんなにじっくり鑑賞したのは初めてかもしれません。
線の強弱や、微妙な筆のリズム、手のひらでこすったような跡、
踊り子のめくるめく動きそのもののなかに入り込まんばかりに食い入るドガの視線、
それに連動した手の動きが感じられた。
また、展示全体がざっくりではあるけれど画家の人生に沿っていることも原因ではないか。
音楽を愛する若いドガが、踊り子たちの練習場や舞台に通い、
彼女たちの動きや舞台の空気を表現しようとしたこと。
30年以上も同じテーマを追い続け、
そのなかで巡り合わせた写真や映画というテクノロジーとの躊躇いがちなしかし先見の明ある受容。
晩年になって視力が衰え足腰が弱まり、もはや劇場に行くことすらできなくなっても、
自分の記憶のなかで踊り子たちの動きを再生し、それを色の世界で表現しようとしたドガ。
きれぎれになりがちな分析的構成の背後に、有機的につながった芸術家の魂が透けてみえる。
しかし、なぜ、生涯にわたってバレエの踊り子たちを描き続けたのでしょう。
当時のバレエダンサーたちは、現在のようにハイカルチャーではなく、むしろ社会の低層に属していました。
富裕層出身のドガが踊り子たちを対象としたことが疎まれ、
その構図は覗き見を思わせ猥褻だという批判の声もありました。
彼が描いた「アブサンを飲む女」が、イギリスの印象派展ではじめて紹介されたとき、
退廃的な題材だという理由で非難囂々だったことも重なります。
(その攻撃のお先棒を担いだのが他でもないロイヤル・アカデミーの会員だったことは歴史の皮肉としかいいようがありません)。
踊り子を選ぶわけは、
バレエが「ギリシアのムーブメントをよく表しているから」と、
彼自身がこたえていることが、展示の最後のほうで解説されていました。
彼の口からムーブメントという言葉が出てくるのは至極ごもっとも。
では、「ギリシア」とは何でしょうか。
そのことについて、展示はあまり詳しく触れていません。
ただ、ギリシアの踊り子たちを描いた作品群の展示室へと招くばかりです。
バレエとギリシアにはなんの関係もない。
ですが、印象派の先駆けにあったドガが自らを「現代生活を描く古典画家」と自称していたことを知れば、
「ギリシア」とは古典芸術を意味することが推測できます。
ヨーロッパでは永年にわたって、ギリシア・ローマの古典が人間が到達した最高芸術だと考えられていました。
つまり、ドガは、あくまでも正統的な芸術的探究に根ざしつつ、
時間の芸術を非時間の芸術に表現しようという野心の火を静かに燃やしたのであり、
そのためには、バレエの踊り子たちが最適のモデルと考えたのではないかと思うのです。
死の二年前のこと。
ドガは彼を撮影させてほしいという若い映像作家の申し出をはねつけました。
断られた映像作家はひるまず、こっそりカメラを据え、
パリの通りをステッキを持ちながらこちらに向かって歩いてくる80歳の老画家をフィルムにおさめました。
展覧会の最後は、生涯をかけて「動き」を捉えようとした画家自身のゆっくりとした歩みで終わります。
この冬、アメリカのボストン美術館でも「ドガ展」が開催されています。
幸い、数日後、ボストンに旅たちます。ここではどんなアングルでドガが描かれているか楽しみです。
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
観光の個人ガイドのほかに、現地日本人向けの文化講座や、文化関係の通訳やミュージアム資料調査の代行も行っています。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。






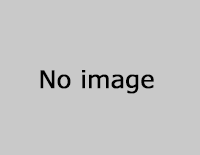








コメントを残す