アフリカのシェークスピア
このブログの主たるテーマは展覧会・美術・ミュージアム関連にあるのですが、
今日は無礼講をお許し下さい。先日ストラッドフォード・アポン・エイボン(英国)のロイヤル・シェークスピア劇場で観た演劇のことを、ぜひともお話したいのです。
鑑賞したのはロイヤル・シェークスピア・カンパニーによるシェークスピアの「ジュリアス・シーザー」。
演出をやっている友人といっしょに観たのですが、その友人が彼女のブログに書いてくれていますので、演劇評についてはそちらにお任せするとし、わたしも、記憶の冷めやらぬうちに、わたしの観点から書き留めておきたいと思う次第です。
それは「アフリカ」という観点です。
この「ジュリアス・シーザー」は、手の込んだ舞台装置やサーカス的な要素や映像の活用など一切なく、台詞もオリジナルの古い英語をほとんど変えていません。言い換えれば、シェークスピアが書き下ろした戯曲にアレンジを加えず、素のままの「演劇」づくりに徹していました。
しかし、演じるのはすべてアフリカ系黒人の役者たち、エキストラの大半もローカルのアフリカ系移民でした。
キャスティングには大きな意味があります。
つまりこのプロダクションは、紀元前のローマを舞台に16世紀の英国人が描いた演劇世界が、どのように現代のアフリカ社会に響くのか、その文脈の中で読み解くことができるのかを、わたしたちに問いかけているのです。
例えば、最初のシーザー凱旋を迎える市民たちのシーンは、観る者の頭の中で、力ある政治家を音楽や踊りで陽気に讃えるアフリカの人々の様子に自然に置き換えられる。
パワーを巡るシーザーと周囲の元老院の人々との摩擦や背信は、アフリカ独立後の独裁者やそれをとりまく権力争い、裏切り、それに続く殺戮を彷彿とさせる。
シーザー暗殺後の有名なブルータスやアントニーの演説のシーンは、パワーが雄弁と密接に結びつくこと、それによって人々がいとも簡単に騙されることを思い出させる。
しかし、ここに善悪の二極はありません。パワーを巡って、それぞれがそれぞれの立場で、己の信条や運命を生き抜いていく。シェークスピアの描く人物像はどれも両義的で複雑だからこそ、真実味に裏打ちされ、登場人物のだれにでも感情移入ができたのかもしれない。同時に、その両犠牲や脆さを役者たちも、実にうまく表現していました。
古代ローマから現代アフリカへの置き換えが、観る者の中で自然になされたのは、演出が戯曲に忠実だからに相違ありません。そしてなにより、そういう出来事や感情を、演じるアフリカ系の役者たちが、直接的にも間接的にも彼らの実人生の記憶に深く刻み込んでおり、パワーをとりまく人間の愛憎や弱さや悲しみや苦しみもよく理解しているからこそ、シェークスピアの言葉が彼らのアフリカ訛りの英語を通して、観客の心に生き生きと響いてきたのではないかと思うのです。
わたしも、いくつかのシーンで、南アフリカに住んでいた時の個人的な思い出と重ねながら観てしまいました。
たとえば、シーザーが数名の暗殺者たちによってメッタ刺しにされた後、その亡骸を囲みながら、アントニーがシーザーの衣装を市民に見せ、この傷はキャシアスによって、この傷はキャスカによって、この傷はブルータスによってなされたのだと示すシーンがあるのですが、
それを見ながら、ケープタウンのタウンシップ(黒人居留区)で知り合った40代の女性が、アパルトヘイト時代、彼女の父親が黒人警官(体制側)であったため、又たいへん頑強だったために、黒人同胞たちに数十箇所も刺されて死んだことを、そして、その彼女が同じ町に今も暮らし、コミュニティーに重要な貢献をしていることを思い出してしまったのです。
飛躍のしすぎと思われるでしょうか。でも、南アフリカの人々にとって、政治的なパワーに巻き込まれ翻弄され、自らも加担し、傷つき、乗り越えていかざるを得ない現実が、劇場の世界ではなく、彼らの日常と背中合わせにあったことに、どうしても思いが至ってしまう。そして、今この時も世界のどこかで起きていることに気付くのです。
このように現在の人の心をうつのは、シェークスピアの戯曲が時空を越えて普遍的であり、そしてそれを十二分に生かした素晴らしい演出と素晴らしい演技、それを支えたアーティストたちのコラボレーションであったからに他なりません。
このプロダクションが、いつに日にかアフリカ諸国を巡り、市井の人々の目の前で演じられるとよいのですが。
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
観光の個人ガイドのほかに文化関係の通訳やミュージアム資料調査の代行も承ります。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。





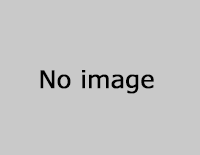






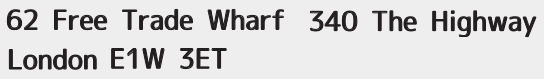

コメントを残す