人生へのオマージュ:レンブラント展
なんという手だろう。
皮膚は干からびて、骨に貼り付いている。
透けて見える骨格は、この老婆の人生が、決してスムーズではなかった事、
一人の人として、
それでも、そのグレイの肌に、ほんのり赤みが差し、
この人の体温や、息づかいを感じる。
まるまった小さな体に比べ、大きく描かれた両手も
彼女の人生の大きさを表している。
老婆は、その手からはみだすような大きな聖書を抱えている。
キャンパス全体が暗く、彼女の頭も黒い頭巾ですっぽり包まれているのだが、
その聖書からは神々しい光が静かに溢れ、
聖書に目を落とす老婆の顔を、まるでスポットライトのように下から照らしている。
その顔は、額に皺が深くより、頬の肉はだぶついて、
手と同じように、彼女の年齢を刻んでいるのだけれど、
目元は少女のようにやわらかく、口もとはゆるやかに開き、
周囲の喧騒から離れ、ただただ自分の世界に浸っているかのようだ。
いや、この老いた女性は、彼女自身の人生の喧騒からも超越した時間のなかにいるのかもしれない。
ここには、聖書の世界に溶け込んでいる無時間と、ひとりの人として生きられた人生の長さの対比がある。
ロンドン・ナショナル・ギャラリーで開催中の「レンブラント・後期」展には、
この画家が得意としたたくさんの肖像画が並んでいた。
レンブラントの肖像画はどれも、モデルの顔に似せることとか、そのステータスや人柄に迫ること、以上の何かがある。
それは、その人の人生そのものを、レンブラント独特の深い色使いの中でオマージュすることだ。
画家自身にとって、それをもっとも追求したのが、自画像の一群ではないだろうか。
若い頃の成功の後、社会は彼が切り拓いていく斬新な表現を認めず、
注文は激減し、破産し、貧困に陥り、家族がひとりひとり他界して、たった一人残されてしまった、
それでも、自分の目指す表現を信じつつ、そんな自分の生を謳歌するのだ。
わたしには、レンブラントの肖像画には、「絵」というメディアには収まりきらない、
もっと深遠な人間の生に対するまなざしがあるように思えてならない。
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
観光の個人ガイドのほかに、現地日本人向けの文化講座や、文化関係の通訳やミュージアム資料調査の代行も行っています。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。






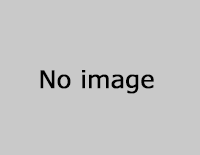






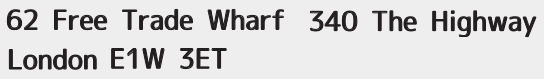

コメントを残す