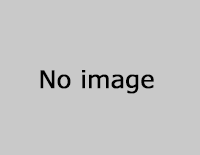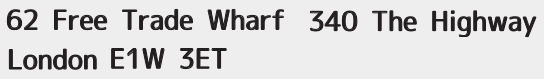1000枚のモネを売った男
日本の人は印象派好きだと思う。
彼らの陽気で、光にみちた明快な絵は、確かにわたしたちの眼を楽しませてくれる。
だけれど、そのスタイルが誕生した頃、社会からはたいへんな罵声を浴びせられた事、
「印象」という名だって、実は、こいつらの絵は、「たかが印象でしかない」という、
当時の批評家の皮肉から生まれた事を知ると、なぜ、こんな素敵な絵が?と首をかしげる方が多い。
絵に限らず、社会の評価は常に変化するものだ。
その意味でも、伝統的な美術のあり方を塗り変えた、若手アーティストの挑戦は賞賛するに余りある。
だが、歴史をかえたのは、ステージに立つ画家だけの功業ではない。
その舞台裏にも、アーティストたちを支え、市場を動かし、新しい鑑賞をお膳立てする、果敢な男がいた。
その名はPaul Durand-Ruel 。パリの画商である。
印象派の展覧会というと、そのアーティストや作品自体に焦点をあてるのが王道だが、
ロンドンのナショナルギャラリーでの展覧会「印象派を創造する」は、その裏舞台に焦点をあてた興味深い内容だった。
まず、画商デュラン-ルエルのドメスティックな側面から、展覧会ははじまる。
ルノワールが描いたデュラン-ルエルの子供たちの絵、モネが描いた彼の家のドア・・・
そこには、彼の居間の写真があり、その空間を彷彿とさせ、
画家と理解者の暖かい人間関係を感じさせる展示になっている。
次に、仕事に対する思い。
まだ20代、父から仕事を受け継いだ時、実はあまりやる気が無かったのだが、
ミレーや、ドラクロワ、ルソーの絵をみてから、この仕事に生きがいを感じるようになったという。
彼の情熱に火をつけたのは、マネの絵だった。
1860年代当時、マネの作品は社会から非難を浴びていた。
だが、やがて印象派とよばれることになる若手画家たちにとっては、目指すべき憧れだった。印象派が生まれる前夜である。
そのマネの絵を何枚も、デュラン-ルエルは買い集めた。常識外れの博打だ。
やがて、マネやピサロに出会う。
それも普仏戦争を避けて亡命していたロンドンで。
彼はすぐに射程を広げ、その若い画家たちの制作活動を、経済的に精神的にサポートした。
だが売れなかった。破綻しかけたことも1度や2度ではない。
その状況をかえたのはアメリカだ。
アメリカは当時急速に経済力を伸ばしていた。
価値感も、ヨーロッパの古い伝統とは一線を画す、新しいものを求めていた。
その市場に印象派のアーティストたちの作風はぴったりあったのである。
今回の展覧会は、1905年、デュラン-ルエルが企画したロンドンでの展覧会の再現で終わる。
考えてみれば、当時のナショナルギャラリーは、アカデミーオブアーツの本拠地であり、
そのアカデミーは、海を渡ってやってきた印象派をコケおろした組織だった。
翻って、今日、当のギャラリーに集まってくる観客たちのほとんどは印象派ファンだ。
社会は変わる。
わたしたち個人の価値感も変わる。
なんだか、自分や社会を鏡でみるような展覧会だった。
ある意味、ナショナルギャラリーそのものが、自分の過去を鏡に映す機会だともいえる。
追記:この展覧会では、個人蔵の作品がたくさんあり、決して普段はみられない絵が並んでいる。
それもこの展覧会のプラス面である。