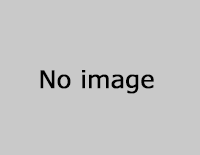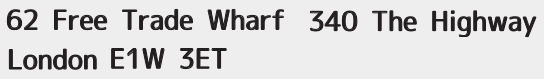パルテノン神殿と大英博物館
「他国のお宝を、もってきちゃったんですね! 世界の大泥棒ですね」大英博物館で歴史教室をしたり、観光のご案内しているとそんな風に言われることがある。
確かに、そういわれても仕方ないのかもしれない。
でも、そうも言い切れない側面がある。
2018年4月、25年ぶりに、アテネのパルテノン神殿を訪れ、その思いを強くした。
同時にミュージアムの研究者として、観光地になった文化遺産とミュージアムの関係について、文化遺産と国民意識について改めて考えるきっかけにもなった。
青い空の下、黄や赤の花々が咲き乱れるアクロポリスの丘に登った。壮大な大理石の建物を再び目前にして、その存在感、環境との響き合い、文化や時間とのつながりを五感で感じとり、ただただ圧倒された。25年前の春と同じように。
それは、ロンドンの大英博物館では感じえない身震いだ。
だが、はっきり言って、そこにあるのは、いわば建築の骨組みだけ。
芸術的価値のある彫刻群はその場になく、半分以上は18世紀末までに、さまざまな理由で壊されたり、崩れたりした。
残されたうちのかなりが、イギリス人トルコ大使、エルギン卿に買い取られ、最終的に大英博物館に寄贈された。19世紀初めの事だ。
その後、アテネにはわずかな彫刻が残ったが、それらも、今はアクロポリスの丘ではなくて、目と鼻の先に建てられた新しい博物館にある。
アクロポリス遺跡の重要な資料を保管展示する施設、文字通り、「アクロポリス博物館」だ。
25年前はなかったこのミュージアムに、今回はじめて訪れた。
重要な展示は最上階にあると聞き、まっすぐそこまで上ってみる。
果たして、そのフロアーはパルテノン神殿とほぼ同じスケール/形状になっていて、まるで本物をそっくりうつしたようだ。
東西の破風に入っていた彫刻群や、ぐるりと二重にあるレリーフ作品が東西南北や位置も正確に設置されている。
といっても、展示されているのは、
本物の断片か大英博物館にある本物のコピーである。
前者は、風雨にさらされて、ほとんど見る影もない。
後者は、コピーであることがすぐわかるような代物で、全く生気がない。
かたや、大英博物館の方は、破損があるとはいえ、作品はどれもとても美しく、生命力が感じられる。
決して贔屓目に言っているのではない。本当にそうなのだ。
エルギン卿が買い取らなかったものは、そのまま20世紀に至るまで、そのまま野ざらしだったために、そこまで破損してしまった事が、心痛いくらい見て取れた。
もし、あの時買い取らなかったら、私たちは、素晴らしい人類の遺産を失っていたに違いない。ある意味、アテネの文化遺産はこの一イギリス人によって救われたとも言えまいか?
今回、この古都に残る彫刻群を自分の目で確認し、脳裏に焼き付いている大英博物館の作品たちと比較できたからこそ、改めて確信することができた。
その一方で、返して欲しいという、ギリシャ側の要求もよくわかる。エルギン卿が買い取った当初、ギリシャはトルコの植民地だった。イスラム教徒であるトルコ政府にしたら、偶像ばかりの神殿に興味はなかったのだろう。それよりズバリ金が欲しかった。しかし、そのすぐあとに、古代ギリシア時代以来はじめて、ギリシャは独立を果たした。
そんなギリシアにとって国民意識のシンボルであるパルテノン神殿は代え難い遺産にちがいない。
2004年のアテネオリンピックに合わせて、鳴り物入りでこのアクロポリス博物館を作った背景もそこにあるのだろう。
ところでこのフロアーは全面ガラス張りになっていて、その向こうに、アクロポリスの丘にある本物のパルテノン神殿を望む事が出来る。来館者は窓の向こうに、そのオリジナルのセッティングをみながら、彫刻群を間近で鑑賞できるように工夫されている。
なかなか考えられた演出だ。
大英博物館にある展示物がどんなにすばらしくても、こんなセッティングは真似できっこない。
現場にあるこその強みを活かしている。同時に文化保存の重要性を啓蒙してもいる。
思えば、この例に限らず、ミュージアムにあるものは、全てオリジナルの文脈から剥ぎ取られたものだ。
遺産は本来あるべき土地にあるほうがよい。心情的にはそう思う。
その一方で、どんなものでも、特に大理石のような自然素材は風雨にさらされるだけで、時とともに朽ちていく。
わたしたちの子孫に先祖の遺産を残していくためには、保管保護は必須なのだ。
そしてギリシャという国家も、古代にあったわけじゃなく、近代に創られた概念であり枠組みだ。
パルテノンはギリシャの遺産であり、同時に人類の遺産なのかもしれない。
これからは、そんな思いを持って、大英博物館のご案内をしよう。