ピナ・バウシュヘのオマージュ:Pina 3D
80年代の終わりだったか、
始めてピナ・バウシュのダンスを見た時の衝撃がきのうのことのように思い出されます。
あの時も映像だった―「カフェ・ミュラー」。
バウシュは、ダンスと演劇を融合させたことで世界的な評価を得たわけだけど、
私の感動はその観点からではなく、むしろダンスの動きそのものからくるものだった。
それまで私が知っていたダンスは、
鍛えられた身体の、円弧を描くようなスムーズな動きや調和、リズム、力強さで表されるものでした。
しかし、バウシュや彼女が率いるヴッパタール舞踊団の表現は、それとは全く違う。
調和を拒絶してみることから始まるダンス。
ある体の動きから、ふつうならそうは繋がらないだろうという別の体の言葉が紡がれていく。
そこには、動きの不器用さ、病的ともいえる痙攣・反復、たどたどしさ、
自分でコントロールできないほど「もどかしい身体」そのものが、あけすけに表現されていた。
また、そこで表される人間関係も、けして陳腐な展開ではない。
むしろ、衝突や葛藤、自虐、あるいは受容などがエンドレスに語られ、
あまりに日常的だからこそ、いとおしささえ感じた。
そうした動きや関係性の緊張からひとつの詩が生まれる。
緊張が解き放たれたときには、ユーモアが弾き出される。
バウシュは、そうした諸々を慈愛で包み、
身体の強さと弱さを、存在の重さと軽さを、みごとにダンスの世界に表したのです。
2009年夏、バウシュは他界しました。
同国の映画監督、ヴィム・ベンダースは、長年の苦闘のあげく、彼女へのオマージュをフィルムに納めることに成功しました。「Pina
3D」です。
日本でももうすぐ公開されるそうなので、この映画について細かく書くのは控えたいと思います。
ただ、一言だけ賛辞を言わせてください。
ここに描かれたバウシュの世界はどれをとっても感動的なアーカイブです―舞台の内も外も。
しかし、黒子役に徹したベンダースの映像もまたすばらしい。
彼自身が言うように、3Dというテクノロジーを使ってしか、
彼女の舞台を映像に再現することは不可能だったのでしょう。
と同時に、そのテクノロジーという手段を見る者にほとんど意識させることなく、
バウシュへのオマージュを彼独自の映像空間のなかに作り上げています。
ところで、映画の最後に、舞台の小さなスクリーンに写るのは、
「カーネーション」の時のバウシュのソロではないかしら。
大阪の舞台もピンクの花で埋め尽くされていましたっけ。
地平線の向こうに
黒い母がいる
たった一人で立っていて
魚のように
手を振っている (1998.魚たちのダンスから Yuuki)
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、ロンドン現地にて、ユニークな文化の旅の企画・ご案内や日英のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
観光の個人ガイドのほかに文化関係の通訳やミュージアム資料調査の代行も承ります。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。





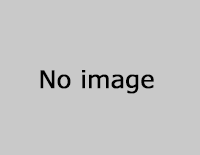






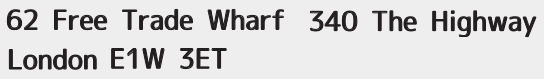

コメントを残す