pussan
2000年、ロンドンにオープンしたTATE Modenは、19世紀のモネの油彩画とイギリスの現代美術作品の組み合わせなど、違う文化背景の作品をいっしょに並べるという展示構成で、世界にあっといわせました。
作品を歴史に沿って構成するのが常道だったミュージアムは、それ以来、時に物議をかもしながら、異質なもの同士を並べてみせる、という試みを始めたのです。
展示の歴史構成が近代モダンの考え方をもとにしていたのなら、このような構成を「ポス ト・モダン展示」とでもいうのでしょうか。
新しい展示構成は、ミュージアムのチャレンジにちがいありませ ん。
では、それを受けとる鑑賞者にとってはどうでしょう。
うまくいけばとっても新鮮で刺激的。外れてしまえば、意味をなさなかったり、惑わ すだけだったりします。
鑑賞者とコミュニケーションがつくれなければ、せっかくの試みは水の泡。
その意味で、21世紀のミュージアムはモダニズムの視点から離れて新しい方向性を探りながら、コミュ ニケーションをいかに大切につくっているかが問われるのです。
そんな中、先日、その試みが成功したすばらしい展覧会にであいました。
ロ ンドンのDulwich Picture Galleryで行われた「サイ・トゥオンブリーとプッサン:アルカイダの画家たち」という特別展です。
かたや17世紀のフランス画家、かたや現代のアメリカのアーティスト。文化背景も違えば、もちろん表現手法もまったく異なるふたり―どうみてもミスマッチ に思えます。
実は、この展覧会、ツォンブリーの次のような言葉をきっかけに生まれたものでした。
「もし生まれ変わることができたら、わたしはプッサンになりたい。」
サイ・トゥオンブリーはプッサンの熱烈な敬愛者だったのです。
人生も関心も重なります。ふたりとも30代前半にイタリアに拠点を移し、
「ギリシア神話」など古典的なテーマを創作活動のなかで掘り下げました。
たとえば、この組み合わせ。
左はプッサンの「リナルドとアルミダ」、右はトゥオンブリーの「ヴィーナスとアドニス」です。
どちらとも、愛憎の絡み合う恋人たちを描いています。
ふたりの作品が小さな展示室の向かいあわせに掛けられているからこそ、寓意にあふれ崇高で静謐な画面の奥から、アルミダの引き裂かれた情念がふつふつと聞こえてくる。
恋人の寝顔をみる熱いまなざし、その髪をやさしく愛撫する左手と、、、もうひとつの震える手。(画面がきれていますが、彼女は右手にナイフをもっています。)
白い大理石のような胸のうちは如何ともしがたい愛憎の炎がたぎっているのです。
ふたつの作品が隣接しているからこそ、トゥオンブリーの激しい筆の動きや色のぶつかり合いに、愛と死という永遠のテーマが浮かび上がってくる。
この赤はヴィーナスとの愛の時間であり、彼女の夫によって殺されたアドニスの血であり、その死から生まれたアネモネなのでしょう。
従来の展示構成を踏まえれば、同じ美術館でさえみることのできない作品同士が、
このように並ぶことによって、それぞれの作品がより豊かに語りかけてくる、
作者が言わんとしたことの深層がみえてくる、、、そんな気がしました。
批判の声も、もちろんありました。
まったく違う手法の作品を並べることでお互いのよさを損ねているとか、
来館者をクレージーにさせるだけだとか。
たしかに、時代や流派に沿った構成によって、
アーティストのスタイルの微妙な違いや美術の発展というものを知ることができます。
しかし、スタイルはあくま でも表現の手段。
耳を傾けるべきは、その奥にある芸術家のメッセージであり、それをいかに視覚表現で表そうとしたかという独自のクリエイティヴィティです。
この展覧会は、手段ではなく芸術家の内面に注目することで、ふたりの作品を結びつけ、それによって彼らのメッセージだけではなく、実はそのアプローチのしか たそのものを浮かび上がらせたのではないでしょうか。
わたしにはクレージーどころか、二人の表現の織り成すハーモニーが時空を越えて響きあっているように思えたのです。
実は、この展覧会が始まって一週間も たたないときに、予期せぬ訃報が届きました。
サイ・トゥオンブリーがローマで死を迎えた。83歳でした。
この展覧会は、彼の作品がプッサンと並べて展示された 始めての展覧会でした。
Dulwich
Galleryでの展覧会は、図らずも、プッサンを愛したこのアメリカの芸術家への最高のオマージュになったのです。
Dulwich Piture Gallery/ London : 29.06.2011 -25.09.2011
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、現地ロンドンにて、個人旅行の企画・ガイドや
日本/英国のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
個人ガイドのほかに文化関係の通訳やミュージアム資料調査の代行もしております。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。






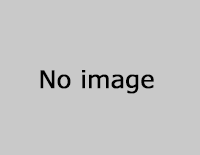






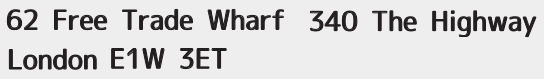

コメントを残す