裏返しの神の家 ロンドン・ナショナル・ギャラリー
美術館というものが世に現れる前、市井の人々が絵画に出会ったのは、西洋では「教会」をおいて他にありませんでした。教会の絵画は総じて宗教画ですが、同じ一枚の宗教画が、「美術館」の壁に掛かっているのと「教会」のなかで飾られているのでは、出会いや見え方は相当異なるでしょう。それを「美術館」のなかで問うたのが、ロンドン・ナショナル・ギャラリーの「神に捧げるデザイン」展でした。
中心に位置する展示室では、中世イタリアの教会内陣が再現されています。部屋の暗さに目が慣れると、周囲の壁に15世紀以前の宗教画がぼんやり見えてきます。でも、圧倒的に視線が注がれるのは、擬似祭壇の上、蝋燭で照らし出された大きな祭壇画。その前には、美術館のベンチが、まるで祈祷のベンチのように並んでいる。
そこに腰掛けて、金色の額で縁取られた聖母像をみていると、キリスト教信仰者でもないのに崇高な気分になってくる、、、なんて、そんなわけはない。え?わたしがひねくれ者だから?いや、それだけではなくて、どんなに忠実に再現していようが、ここは美術館だということ、その聖母像が美術館のコレクションだということを頭がちゃんと認識しているからです。
でもせっかくだから、ベンチに腰掛けたまま、教会でみるのと美術館でみるときの絵画の受け入れ方の違いを、ちょっと想像してみようではありませんか。

まず、観るものと絵の位置関係。教会の場合は、絵とのあいだに距離があります。しかもかなり高い位置にある。照明も美術館のように一様に明るくはない。蝋燭の光のゆらめきのなかで、絵の背景や聖人たちの光背にふんだんにつかわれた金箔が、賛美歌とともにハーモニーを奏で、キリスト像や聖母像を浮き上がらせたことでしょう。絵画は、地上における天上界を演出する教会装置の一部として機能しました。
かたや、美術館では、一枚の絵画はそれそのもので独立し、鑑賞者と一対一で向かいあいます。観る者は、そのディテールを作り手のタッチを読み取り、その絵がどのような背景で描かれたのか、画家たちの内面や表現技法を捉えようとします。そのような鑑賞に見合うように、美術館は均質な光で満たされ、その鑑賞の助けとなるよう解説ラベルが備えられ、時代や地域毎に配列されました。それとも、逆か?美術館装置がかような演出をしたから、近代的な鑑賞が生まれたというほうが、あるいは正しいのかもしれません。実は、そんな情報は、教会というセッティングにおいては、どうだってよいことなんですが。
そもそも、教会や美術館を訪れる人は、はじめからそれぞれの場の機能を承知の上で、目的をもってそこに立ち入っていく、っていう前提がある。そこで体験することは、あらかじめ訪れる者の意識のなかで想定された体験なのです。
「神に捧げるデザイン」展で教会の忠実な再現があっても、ナショナル・ギャラリーを訪れたという、もっと大きな意識の枠組みの中で、わたしはわたしの体験を認識するのです。だから、すなおに崇高な気分には、どうしたってなり得ない。もちろん、鑑賞者を崇高な気分にさせることがこの企画展のねらいではありませんが。
これまで挙げてきた違いは、今更とりたてて述べるまでもないかもしれませんね。でも、せっかくだから、いま一度15世紀にタイム・スリップして、もうすこしだけ想像を膨らませて比べてみようではありませんか。
当時の人々が教会を訪れることは、21世紀のわたしたちが超ポスト・モダンの美術館にはいる以上に、とてつもなくスペクタクルな体験だったのではないかと思うからです。
そう考えさせる要因は、教会の演出や機能、訪問するときのわたしたちの意識からくるだけではありません。教会をとりかこむ社会がどのような環境であったかということにも考慮すべき要素があります。
現在、わたしたちの日常はありとあらゆるところにイメージがあふれています。コンピュータを駆使した映像も、斬新なデザインの建築物も、生活のすみずみにあふれる広告も、一昔前と比べたって比較にならないくらい目も脳みそもイメージの海にどっぷり浸かっています。
ところが、宗教画が描かれた時代は、よっぽど裕福でなければ、絵画とか彫刻とか、いや、イメージといわれるもの一般とは、縁遠い社会だったはず。
そんな世界に生きていた人々が、教会のなかにひとたび足を入れたときの体験は、現代人には想像もつかないほど、圧倒的に抗しがたく、それだけに畏怖の念を抱かせるものだったのではないでしょうか。そしてそれが宗教的体験だと思われたのでしょう。
美術館のなかに、中世の宗教画をとりいれられるようになったのは、ルーヴル美術館が最初でした。このことには、ふたつの時代背景が関与しています。ひとつはフランス革命、もうひとつは美術史などの学問を生み出した近代性です。ルーヴル美術館はフランス革命の落とし子といわれます。ルイ家の至宝や王政時代の貴族たちの美術品と同様、前時代の権力者である聖職者たちの財産つまり教会の宗教画なども、革命政府によって没収されました。それらの行き先はやがて公開されることになる美術館(かつての王宮)だった。
権力と結びついていた教会は、フランス革命精神とは相容れないものでした。さまざまな宗教行事が中止されたり「自由の女神」が誕生したのはそのためです。また、ナポレオン軍がヨーロッパ各地で勝利をおさめ、その戦利品としてたくさんの文化財産を略奪してきたのは有名な話です。教会や修道院からも美術品が剥ぎ取られ、パリに運び込まれました。その数があまりに多すぎて、ひとつの美術館では管理しきれないほどだった。ルーヴルのあと、フランス国内外につぎつぎと美術館が建てられましたが、その背景にはそんな事情もあったのです。
フランス革命は、近代性の幕開けでもあります。近代性とは、前時代の神学的・迷信的な精神から解き放たれ、すべてのものを理性の光のもとに照らそうという志向です。かつて教会の一部であった宗教画もそのコンテキストから抜き取られ、美術館という近代性の均質な光のもとに公開されました。教会ではただ朽ちるばかりになっていた絵画が、近代的な修復技術で甦りました。中世の絵画も、「美術史」という近代学問のタイム・シークエンスにおいて、あるべき位置をあてがわれました。そんななかで、表象や受容のしかたも、神への崇高な祈りから科学的なまなざしによる解釈へと変わったのです。
「神に捧げるデザイン」展は、従来の展示とはアプローチの違う興味深い試みでした。でも、美術館のなかで、教会における宗教画体験を見直すという、いわば裏返しのまなざしそのものが、やはり近代性の思考に他ならないのではないか。その意味では、実に美術館的なアプローチだったといえるのかもしれません。ありゃ?ちょっと論点がこんぐらかっちゃいましたね。ともかくも、企画展会場をでたあと、ギャラリーの常設展示の中世宗教画のセクションに行ったときに、そこに掲げられた宗教画が違う角度から見られたことは、大きな収穫でした。
National Gallery (London) Devotion by Design 06/07/ 2011 – 02/10/2011
このブログは、アートローグのディレクターによって書かれています。
アートローグは、現地ロンドンにて、個人旅行の企画・ガイドや
日本/英国のミュージアム・コーディネートの仕事をしています。
サービス全体にご興味のある方は、下のロゴ(ロビンといいます)をクリックして下さい。





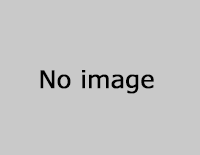






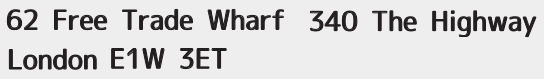

コメントを残す